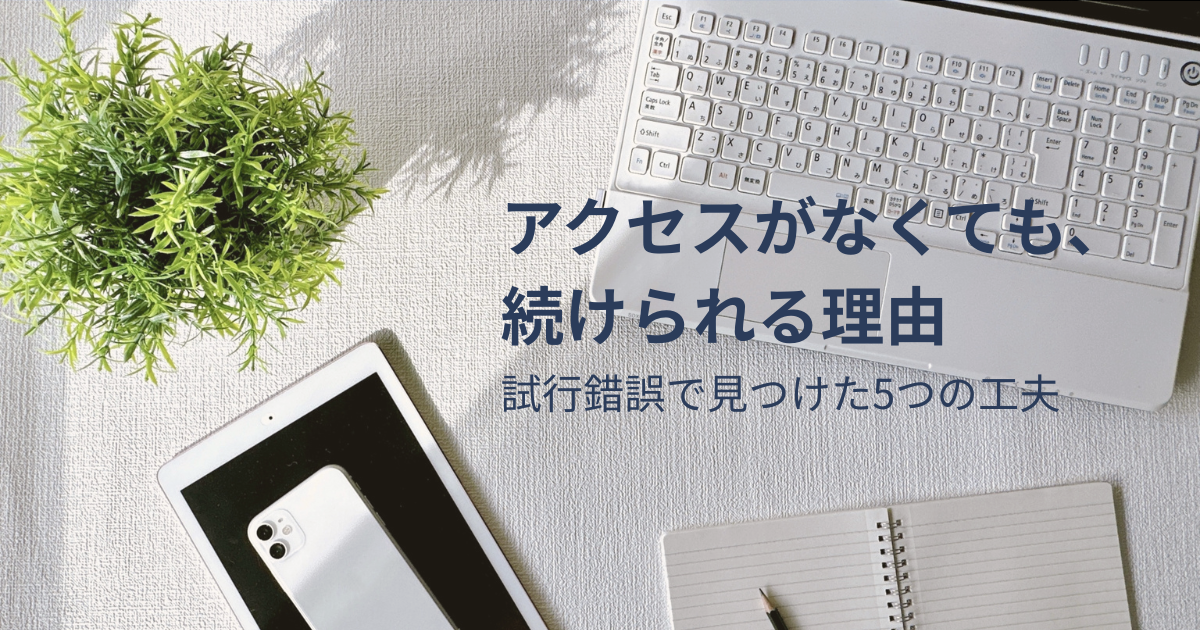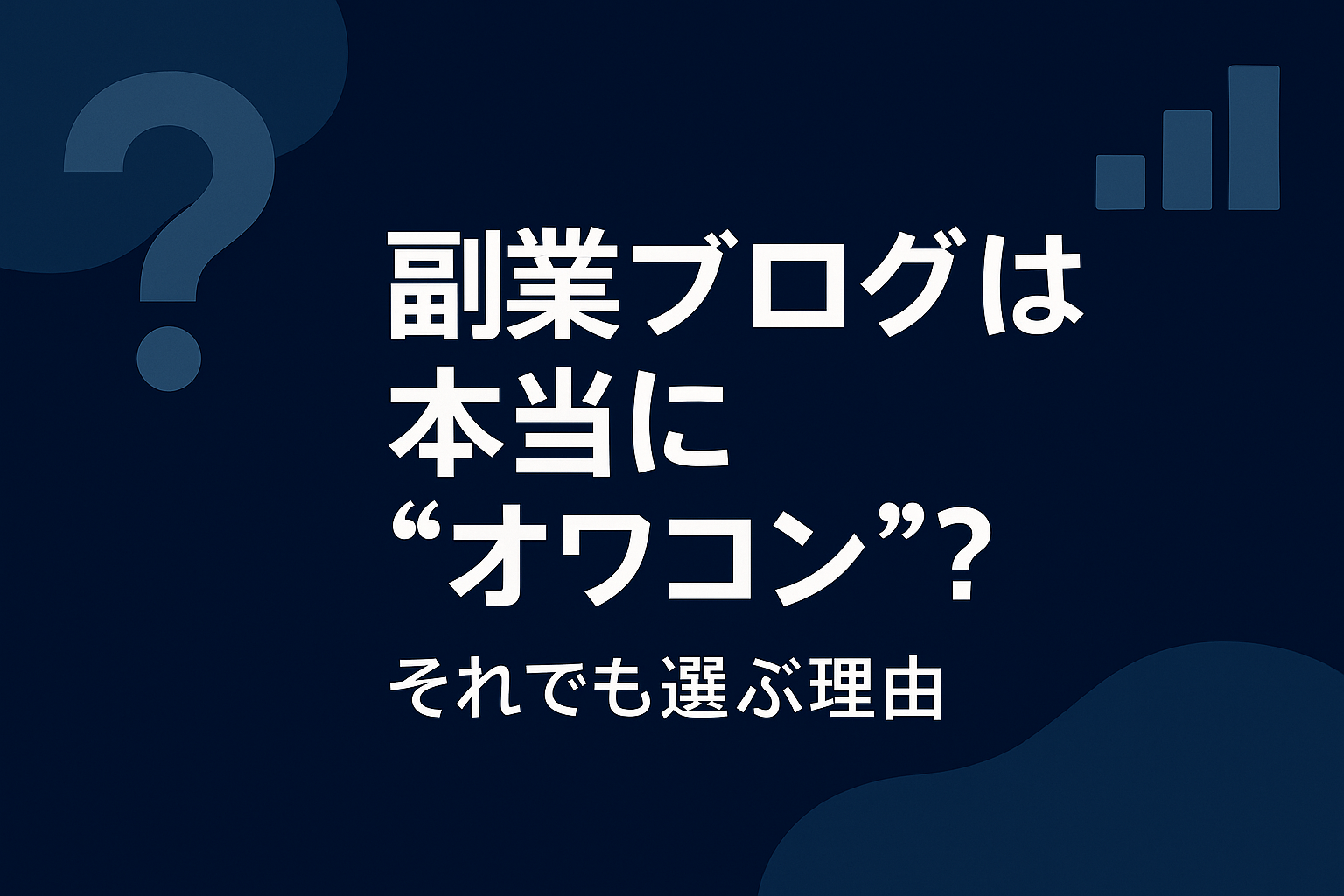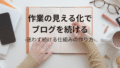ブログを書き始めたばかりのころ、アクセスがほとんどない状態が続くと、「このまま続けて意味があるのかな」と感じることがあるかもしれません。
実際、私自身もそうした時期が長くありました。
誰かに届いている実感がない。読まれている気がしない。
そんな中でも更新を続けられたのは、数字とは別のところに目を向けていたからです。
この記事では、アクセスが少ない状況でも無理なく続けてこられた理由と、小さな工夫を5つご紹介します。
同じような状況にいる方にとって、少しでも参考になればうれしいです。
アクセスが伸びないと、ブログはつらく感じる
どれだけ時間をかけて記事を書いても、アクセスがなかなか伸びない。
その状態が続くと、更新する手が止まりそうになることもあると思います。
自分もその一人でした。
記事を公開しても、リアクションはゼロ。ダッシュボードを見ても、数字がほとんど動かない。
「これ、誰かに届いてるのかな」と思いながら、それでも更新を重ねる毎日は、正直しんどいものでした。
とはいえ、そんな中でも続けてこられたのは、「アクセスがないからやめる」ではなく、「アクセスがなくてもやれること」を見つけていったからです。
ここからは、当時の自分が支えられた考え方や、続けるために意識していた小さな工夫をまとめてみます。
① アクセスより「記録」に意味を持たせた
記事を公開しても、反応がない。
何日経ってもアクセス数がほとんど変わらないと、やっぱり少し落ち込みます。
「これ、本当に意味あるんだろうか」と思ってしまうことも、正直ありました。
それでも書き続けられたのは、途中から「記録すること」自体に、少しずつ意味を感じられるようになったからです。
たとえば、「今日はここまでできた」とか、「このときこんなことで迷ってたな」とか。
思考の跡が言葉として残っていくと、自分の中で点と点がつながっていく感覚があります。
もちろん、読まれることをまったく気にしていなかったわけではありません。
むしろ、届いてほしい気持ちはずっとありました。
でも、届くまでのあいだ、自分なりに確かめながら進んでいるという感覚が、続けるための支えになっていたと思います。
すぐに結果が出なくても、書いたことはちゃんと残る。
それが、思っていた以上に心強かったのを覚えています。

② 「誰か1人」に向けて書く意識を持った
アクセスが少ない時期、いちばん迷っていたのは、「誰のために書いているのか」がぼやけていたことでした。
何となく多くの人に届いたらいいな、と思いながら書いていたけれど、
誰にも届いていない気がして、言葉の重みも自分の気持ちも、どこか曖昧になっていた気がします。
そんなとき、ひとつの転機になったのが、「たった1人のペルソナ」を思い浮かべるようにしたことでした。
ペルソナとは、記事の受け手として想定する“具体的な誰か”のこと。
過去の自分でもいいし、ブログを始めたいけど何から手をつければいいかわからない人でもいい。
輪郭のある「ひとり」を思い描くだけで、文章の方向がはっきりしてきました。
広く届けようとするほど、言葉がぼやけてしまうことがあります。
だからこそ、「この人にだけは届いてほしい」と思える存在を決める。
それが、自分にとって書く意味を取り戻すきっかけになったように思います。
関連記事:ペルソナの考え方や設計方法はこちらにまとめています。
・ 伝わる文章は設計から始まる|ペルソナを活かした文章作成の基本
・ ペルソナ設計から成果を引き出す|実践的なコンテンツ作成法
③ 作業の「見える化」で迷わず進めた
アクセスが少ない時期は、「そもそも何を書けばいいのか」「どこまでできているのか」が分からなくなって、手が止まりそうになることが何度もありました。
迷いながら画面と向き合っている時間が長くなると、それだけで疲れてしまう。
うまく言葉にできないまま、そっとブラウザを閉じた日もあります。
そんなとき、少しずつ意識し始めたのが、「作業を見えるかたちにしておくこと」でした。
記事構成を先にざっくりでも書いておく。
「今日はタイトルだけ考える」「H2を3つだけ決める」など、作業を小さなステップに分けておく。
思いついたことや、後で書き足したい要素をメモとして残しておく。
一つひとつはたいしたことではないのですが、これらを事前に用意しておくだけで、
「今はこれだけやればいい」と思えるようになり、気持ちがぐっと楽になりました。
完璧な文章をいきなり書こうとするより、まずは道筋をつくっておく。
それだけで、迷いが減り、「書けない自分」に振り回されなくなったように思います。
今振り返ってみると、当時やっていたことは「効率化」ではなく「不安を減らすための準備」だったのかもしれません。
うまく進まないときほど、自分が迷わず動ける環境を整えておくことが大切だと実感しました。
関連記事:
・ ブログが続かない人へ|「作業の見える化」で迷わず進める仕組みづくり
④ 小さな反応やアクセスも、ちゃんと嬉しかった
アクセスがなかなか増えない時期でも、ごくわずかな反応が見えることがあります。
たとえば、1件だけアクセスがあった日や、内部リンクをたどって別の記事まで読まれていた形跡を見つけたとき。
それだけでも、少し気持ちが変わる瞬間があるかもしれません。
「誰かがこの記事を開いてくれたのかもしれない」
その小さな事実が、数字以上の意味を持つこともあります。
たとえ成果が出ていないと感じるときでも、ほんのわずかな反応が「もう少し続けてみようかな」という気持ちにつながる。
そんな経験は、きっと多くの人にとって覚えがあるのではないでしょうか。
ブログは、すぐに結果が出ないことも多いけれど、
そうしたささやかな反応が、静かに背中を押してくれることもあると思います。
⑤ 続ける「環境」を自分でつくっていた
ブログを続けるうえで、自分のやる気や気分にすべてを委ねてしまうと、どうしても波が出てしまいます。
特に、成果が見えにくい時期は「今日はやめておこう」が何日も続いてしまうことも。
だからこそ、「書ける環境」を自分の中につくっておくことが大切だと感じました。
たとえば、集中しやすい時間帯を決めておく。
1日30分だけでもブログに向き合う時間を確保しておく。
作業のハードルを下げて、「とりあえず開くだけ」「タイトルだけ決めて終わる」などのゆるいルールをつくっておく。
少しでも“触れる”状態を保っておくと、完全に手を離さずにいられます。
ブログに限らず、何かを続けるときは「気持ち」より「仕組み」のほうが頼りになることもあります。
自分にとって続けやすい形を少しずつ見つけていくことで、無理なく続けられる感覚が持てるようになりました。
関連記事:
・ 続けるための環境と仕組み化|無理なく進めるための考え方
続けるための環境を少しずつ整えていくと、取り組み方にリズムが生まれてきます。
ただ、そうした仕組みをつくっていても、「今日はどうしても書けない」「やる気が湧かない」と感じる日が出てくることもあります。
調子がいいときばかりではない。
むしろ、そうではない日のほうが、後から振り返って大事だったと感じることもあります。
では、モチベーションが下がってしまったときは、どうすればいいのでしょうか。
次に、そんなときの向き合い方についてまとめてみます。
モチベーションが下がったときの対処法
やる気が出ない、手が止まる。
そうした日は、どれだけ準備を整えていても出てくるものです。
気持ちが動かないときに無理に立て直そうとすると、かえって負担になってしまうこともあります。
だからといって、そのまま完全に手が離れてしまうと、再開するときのハードルが高くなりがちです。
少し距離が空いたとしても、また戻れればそれで十分。
そのときのために、「再開しやすい状態を少しだけ残しておく」という工夫は役に立ちます。
- タイトルだけ決めて下書きに保存する
次に開いたとき、「ゼロから考えなくていい」状態をつくっておく。 - 記事の構成をざっくりメモしておく
思いついた内容を記録しておくだけでも、再開の助けになります。 - 管理画面だけ開いてみる
書かなくてもいい。ただ“見る”だけでも、自然と気持ちが戻ることがあります。 - テーマの断片だけメモに残しておく
まとまっていなくても、考えていたことの痕跡を残しておくことで、次につながります。
書けない日が出てくることもある。
そんなとき、「何もしない」ではなく「できることを少しだけ残しておく」。
そういった関わり方をしておくだけで、次の一歩が少し軽くなることがあります。
まとめ|書いてきた時間は、あとで効いてくる

アクセスが伸びない期間は、なかなか成果が見えにくく、不安や迷いも出てくるものです。
それでも続けてこられたのは、「数字」以外のところに、小さな意味を見出してきたからでした。
すぐに結果が出なくても、書いてきたことは確実に自分の中に残っていきます。
どんなことで迷い、何を考え、どう動いてきたか。
そうした記録があるだけでも、次に進むときの足がかりになる場面はあるはずです。
すべてが思うように形になるとは限らないけれど、
まったく何も残らないわけでもない。
その視点を持てるかどうかで、続ける意味の感じ方は変わってくるかもしれません。
書いてきた時間があとから効いてくることも、きっとある。
そう信じられるだけでも、歩みは少し軽くなるはずです。
著者プロフィール